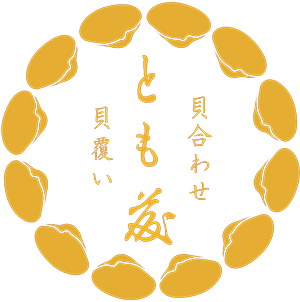平安時代、貝合わせは珍しい貝を持ち寄り和歌をつけてその優劣を競う遊びでした。斎王良子内親王の「斎王貝合日記」(1040年)には貝合わせについての記述があります。
公式な行事として貝合わせの記述が有るのは、1162年、二条院の后、藤原育子(父、藤原忠通)の立后の後に催された貝合わせです。天皇家、摂関家が後見となって開催されました。物語では『堤中納言物語』に貝合わせの詳しい様子が書かれています。こちらは読みやすい現代語訳もありますので、興味のある方は是非読んでみてください。
平安時代末期には「今様」「物合」という遊びが流行しており、貝合わせも「物合」の一つとしてさかんに遊ばれていました。
さて、貝覆いについても記述が残っています。当時は主に宮中で遊ばれていた貝覆いですが、私は先にあげた藤原育子と同時代に生きていた後白河院寵姫、平滋子に注目しています。
平安時代の歌人、藤原俊成の娘、建春門院中納言は平滋子に仕えていました。「たまきはる」という自身の日記の中で、貝覆いや貝桶についての記述があります。
江戸時代の有職故実の学者、伊勢貞丈は「二見の浦」にて六条院高倉院の頃に始まったのではないかと書いています。六条院高倉院の時代は、平清盛や後白河法皇の世でありますので建春門院平滋子などは、おそらく貝覆いで遊んでいたことでしょう。
当時に思いをはせますと、私どもで実際に貝覆いを製作してみると、ゲームが面白く出来るくらいに柄や形、大きさを揃えようとすると貝殻の数はゲームで使用する数の3倍は必要になります。ですので、当初から360個の貝殻で貝覆いをしていたわけではないと思われます。
藤原摂関家の衰退、そして平清盛、平氏の世になり鎌倉時代へと時代が移り変わる中で、物合わせとしての貝合わせは記述がなくなってゆき、貝覆いの記述が増えてゆきます。
『とりかへばや物語』や『源平盛衰記』には貝覆いについての記述があり、鎌倉時代の記述には出貝、地貝に分け、円形にならべて相方を捜す貝覆いが遊ばれていたことがうかがえます。
その後、貝覆いは「歌かるた」のもとになったともいわれていますし、豪華な貝桶や360個の貝殻に源氏物語絵巻などを描いて婚礼道具にしたのは、室町時代頃からのようです。
貝合わせ貝覆いというと平安時代というイメージがありますが、実は平安時代以降も長く遊ばれてきたものです。いつの頃からか、貝合わせと貝覆いは混同されるようになりました。貝覆いでも貝を合わして遊ぶのですから、貝覆いを貝合わせといっても特に差し支えはないように思いますが、未来において平安時代の和歌を詠んだ貝合わせのことを貝覆いだと勘違いされる可能性もありますから、貝合わせと貝覆いが別の遊びであることを私どもではお伝えするようにしています。
五節句の上巳(雛祭)ではもちろんのこと、七夕にも「七遊」として、「歌」「鞠」「碁」「花札」「貝合」「楊弓」「香」が遊ばれていたとも言われています。明治6年(1873年)の改暦の際に当時の政府は式日としての五節句を廃止しました。太陽暦となったことから、本来の五節句の季節と暦の日にちがずれてしまい、五節句が次第に親しまれなくなったのも、貝合わせ遊びをしなくなった原因の一つかもしれません。
貝合わせ貝覆い とも藤
佐藤朋子